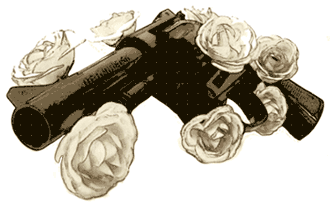 ゆっくりとお風呂に入って残る夜を朝までぐっすり眠りたいなと思う。そうすればもしかしたらこの夜のことが全部夢という形でおさまるかもしれない。
ゆっくりとお風呂に入って残る夜を朝までぐっすり眠りたいなと思う。そうすればもしかしたらこの夜のことが全部夢という形でおさまるかもしれない。
そんなわけ、ないか。
首を振ると何かが抜け落ちてスッキリした気がした。
まだそっとわたしを覗いている鳩の視線を感じていた。
自分の中に生まれて大きくなり始めてしまった好奇心が少しずつ喉元に込み上げてくる。
Z。鳩。ロイド・ジェファーソン。
理由を考えてみると、おかしいかもしれないけれどZが無理にわたしの部屋に入ろうとしなかったから、というのが実はとても大きいんだと思う。冷ややか過 ぎて感じられるほど冷静で行動はかなり強引。だけど、今こうしてわたしは1人で部屋にいる。入ろうと思えばとっくにZはそうすることができたのに。
もしも部屋の中に誰かがいてわたしを待っていたならZが言ったように撃たれるなり何なり怖いことになっていたかもしれない。その辺はまだわたしにはまっ たくピンとはこないんだけど。もしそうなっていたらZはどうしただろう。想像してみてハッとした。そしてチェーンをかけてあるドアを眺めた。きっとこのド アを破ることはZには簡単なことなんだろう。抱えられて突っ込んでくる車から逃れることができたあの瞬間。わたしがZの全身から感じた強さは圧倒的だっ た。
わたしは多分今もZの手の中にすっぽりおさまっているも同然なんだ。だけどこのドアが、チェーンが、気持ちに少しだけ余裕を与えてくれる。自分の頭で考 えることができるだけの余裕を。
「このドア・・・破るのにどのくらいかかる?」
「・・・1秒」
短い響きにちょっと笑った。相変わらず感情は読めなかったけど、でも多分答えるのは面倒くさいのかな、と想像した。
廊下までなら、いいかな。
心が囁いた。我ながら大げさと感じるほどドキドキしていた。
Zの顔をちゃんと見ながら話をしたい。いつのまにか好奇心がこんなに大きくなって、パンクしそうな気がする。そのくせそんな自分がとても不安だ。
迷った。
いいかな、と思いながらやっぱり、と否定した。何回か口を開きかけたけれど自分が何を言いたいのか分からなくてまた閉じるしかなかった。
ああ、馬鹿だ。迷いながら理由も分からず恥ずかしかった。
その時バッグの中の電話が鳴らなかったら、少なくともあと1時間くらいそうして悶々と答えが出ない悩みを自分の中で転がしていたかもしれない。でも、電 話は鳴った。大好きなピアノ曲の一節。これ以上は無理なくらい素早くストラップを掴んで引っ張り出すと、液晶画面には見慣れないナンバーが並んでいた。い つもなら登録していない番号には出ないだけなんだけど。わたしは戸惑いながらまだストラップの先を摘んでいた。携帯電話そのものに触れるのはなぜか躊躇わ れた。
1回、2回。着信のメロディが循環する。その間、わたしはただ表示されている数字を見つめていた。
「知らない番号か」
頷いてからZには見えないことを思い出し、慌てて答えた。うん、と言ったつもりだったのに意味不明な音になってしまった。
「無意味な悪戯ではなさそうだ。出ろ」
Zの言葉に従おうと思ったけれど、指先が震えた。
「そう簡単に電話で人は殺せない。仕込むには時間がかかる」
・・・時間をかければできるということなんだろうか。逆に怖くなったけれど、指は声に従った。
「・・・もしもし?」
囁くと相手のクリアな声が耳に響いた。
『こんな夜中にごめんなさいね。あなたの部屋のセキュリティ装置から通知が入ったので確認をと思って。今、お部屋?それとも外かしら。大丈夫?TX』
落ち着いた女性の声。話の内容からこれは元の大家さんからのものだ・・・と考えるべきなのだろうと思った。
でも。
『もしもし、大丈夫?こんなことならお部屋を譲った時にもっといろいろ細かなセキュリティに変えておけばよかったんだけど。ごめんなさいね。ねえ、 TX?』
確かに話し方も声も大家さんのものかもしれないと思えた。
でも。
気がつけば手が震えていた。
「どうした」
Zの声に我に返った。携帯電話を床に置き、そっとドアの隙間に身体を寄せた。
「・・・この部屋を売ってくれた大家さん、というかそう思わせようとしてる電話だと思う。でも、そんなこと、あるかな。変、だよね?」
「なぜ偽者だと思う」
「わたし、携帯電話、2つ持ってるの。学生の時から使ってるのと会社に入ってからのもの。この部屋には学生の頃から住んでるから、大家さんが知ってるのは 古い方の番号のはずだし・・・何より、契約したときのわたしはまだ『TX』じゃなかった。数字だけのコードだった。大家さんはいつもそっちでわたしを呼ん でた」
「十分な理由だな」
ドアがもう少しだけ開かれ、隙間から入ってきたZの手が上を向いて開いた。そっとそこに電話をのせると手は引っ込み、ドア越しに短い破壊音が響いた。電 話を2つに折る・・・映画で見た1場面が頭の中で再生された。
「・・・Z」
「職場からたどることができるのは手に入って当然のデータばかりだ。無駄に騒ぐ必要はない」
「でも・・・Z」
声が震えていた。Zは沈黙で先を促した。
「最後に大家さんと話したのは随分前だから何もかもうろ覚えなんだけど・・・・でも、今の電話、話し方がとても似ていた気がするの。わたしがこの部屋を借 りてるんじゃなくて買ったことも知ってた」
「不動産関連のデータベースからここの所有者がお前だと知るのも簡単だ。ただ、そうならお前を古い方のコードで呼ぶべきだったとも思うがな」
「もしも・・・もしも、大家さんの話し方を直接確かめてから電話したんだったら・・・?」
「つまり?」
「大家さん・・・大丈夫?」
Zがごく小さな溜息をついたように思えた。
「真夜中に赤の他人を叩き起こす覚悟ができるほど不安なら、話は簡単だ。そいつに電話しろ。確認すればいい」
「あ、そうか」
部屋の中に走って引き出しを探った。鳴ることなどもう滅多にないだろうと予想しながら定期的に充電し続けている古い電話。何ヶ月か前にバッテリーも新し いものに換えた。ゆっくりと目的の電話番号を表示させてボタンを押し、電話を耳に当てて呼び出し音を確認する。応答を待ちながらじっとしていられなくて1 歩ずつ玄関に歩く。
大家さんが出てくれたら何といって謝ろう。こんな時間に電話した理由・・・ちゃんとした理由を早く考えなくちゃ。電気や水道なんかじゃダメ。大家さんは 一見とても上品な老婦人に見える女性だけど、それ以上にしっかりした、という印象を受ける人だ。何でも知っていてわたしのことなどすぐに見通してしまうよ うな感じ。いつも落ち着いていて・・・きっとZといい勝負だ。
呼び出し音は鳴り続け、わたしはとうとうドアのすぐ前まで歩いてきてしまった。
「・・・Z」
また声が震えてしまった。
「出ないか」
「・・・うん」
静かにチェーンを外し、ドアを押し開けた。すぐ目の前にZが立っていた。肩に白い鳩をとまらせて、黙ってわたしの顔を見下ろした。
「・・・まだ出ない・・・Z」
Zはわたしの手から携帯電話を取り上げて切った。
「電話に出られない理由など、いくらでも考えられるがな」
うん。失くしたのかもしれないし、電話をバッグの底にしまったまま忘れているかもしれない。わたしもよくやる。
「どうしてこんなに怖いんだろう。朝になったらかけ直せばいいだけなのにね」
「そいつがお前にとって意味のある人間だということか」
意味。わたしにとっての存在する意味?ううん、そんなこと、わたしには決められない。
「よくわからないけど、わたしに居場所を・・・この部屋をくれた人だから。会うたびに印象的な人で・・・」
「変わっているな、お前の価値観は」
Zは肩をすくめ、クルリと背を向けた。
「住所はわかるのか」
「行ったこと、ある」
人の住処に入ることにとても緊張したのを覚えている。そして、帰る時にちょっと寂しく感じたことも。
歩き始めたZから数歩遅れてついて行こうとした時、ふと気がついてバッグを持ち部屋をロックした。
「地下鉄、もうないね」
Zは黙ったままエレベーターに乗り込んだ。車を拾うのかな。一瞬思ったが、Zは外に出るとそのまま裏通りに進んで行く。そこは高い建物たちの間で常に陰 になる細道で、ごみの収集車が通る時間は他の車の通行が止められる。
Zはゴミ搬出のための大きな扉の隣の窪んだ場所に姿を消した。
「防弾ガラスはないぞ」
声とともに戻ってきた姿は街灯の明かりを受けて艶やかな光沢を見せる何か大きなものを押していた。大きな、とても大きな漆黒のバイク。車の類に馴染みが ないわたしにはちょっと物騒にさえ見える。Zは脱いだコートを無造作に丸めて物入れに入れた。鳩が素早くジャケットの中に滑り込んだ。
「場所を説明しろ」
説明するとZはバイクのメーターらしいものの隣のボタンを押した。夜の空気を切り裂くようにエンジンが唸り声を上げた。やっぱりこれは・・・あまりおと なしい乗り物ではないんだろうな。思わず1歩後退さった時、頭にひどく重たいものを被せられ一瞬前が見えなくなった。それが暗い色のシールドのせいだと気 がついたが、どうすれば開けられるのかわからなくてただふらついた。
「それに・・・乗るの?」
ヘルメットの中でくぐもっていた声は、Zの手がシールドを半分上げてくれたので後半外に開放された。見ればZはゴーグルをつけていて目元が見えない。暗 い夜なのに。それとも、単純なゴーグルではないんだろうか。
Zは唸り続けているバイクに跨り、躊躇うわたしの首根っこを掴むと軽々と持ち上げて自分の後ろに下ろした。エンジンの振動を直接感じ、反射的にZの背中 にすがりついた。怖い。これは・・・かなり怖い。足が地面から浮いていることがこんなに頼りない。
「止めておくか?」
エンジン音の隙間から聞こえたZの声はやはり面倒くさそうだった。
朝になってから電話すれば。ほんの1秒、考えた。
「・・・行く」
完全にエンジン音に負けていたわたしの声がどうやってZに届いたのかわからなかったけど。
Zは背中を向けたまま両側からわたしの腕を掴み、自分の腰に回した。
「落ちるな」
声と一緒にバイクがひときわ大きく唸って駆け出した。怖くて全力でしがみついてしまったことを恥ずかしがる余裕はなかった。初めは息をさらわれて上手く 呼吸することができず、焦った。
Z。
やっと呼吸のコツをつかんでましな気分になった時、はじめてZの体温を意識した。こんな風に人に触れることって、これまでなかった。車に轢かれかけたと ころを助けてもらってから、思えばZの体温を感じる機会が随分あった。指先も、手も、今身体を預けている背中も、全部あたたかい。けれど、これほど近くに いてもZ自身に近づいている気は全然しなかった。それが不思議だった。でも、もしかしたらその現実感のなさに救われているのかもしれない。じゃなかったら 驚きの連続にとっくに目を回してる。わたしは1人が好きで、1人で生きてきたから。
ねえ、Z。なのにどうしてこんなにあたたかいと思えるんだろう。
本当は怖くてたまらないのにね。
スピードを忘れたくて目を瞑った。
瞑る間際に見た街の明かりがとても眩しかった。