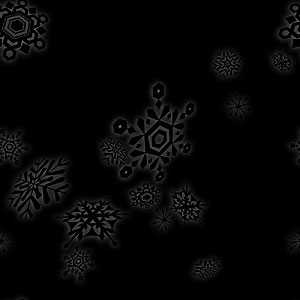 「・・・終わった・・・のか・・・」
「・・・終わった・・・のか・・・」
雪の中に倒れ伏した女の傍らに黒衣の男が立った。
「お前たちを狙う者は少なくともこの山にはもう誰もいない」
「・・・そ・・・うか」
身体に顔を動かす力が残っていないネルは目の前の黒い靴に向かって微笑した。
「・・・言うな・・・
リリアには」
何を言うな、なのか男は問わなかった。男が女から手に入れた海図は昔一人の女海賊が持っていたものだ。自由奔放で機知に富み海の男たちが憧れる対象だっ た女。そして海図はその女が死ぬ前に仲間の一人に渡したものだと言われている。
そう。言われているのだ。
男個人は今回の任務でその噂とは別の仮説を組み立てるに至ったのだが、それは任務とは関係はなかった。
「俺の任務にお前たちはもはや関係ない。あとは海図を持って戻ることだけが俺の仕事だ」
恐らく次に自分が言う言葉がこの世で最後のものになる。それを悟った女はしばし考え、そして息を吐いた。
「・・・そうか」
この男のような人間に無駄を言っても仕方がない。
世界政府が抱えている殺し屋に対してその情に訴える意味はなく、そういう趣味は女にもない。
そしてこの男は契約したことは絶対に守る。
ネルはもう一度息を吐いて残る力を振り絞って目を大きく開いた。胸の中の鼓動が止まったその時に目の前に広がった光景はこの雪山とは別世界の青く広がる 海原だった。
男は生を終えた女を見下ろし、ふとその見開かれた瞳に小さなズレのようなものを見つけた。黒々としていた女の瞳の円が中心から少しずれてその下に何か別 の存在を予測できる。恐らくそれはこの女の本当の瞳の色。長いことその正体も感情も生き様も隠し通した女の真実。
男の口が長く白い息を吐いた。
死体なら今ここにゴロゴロと転がっている。飛び散った鮮血とともに白い雪の中に埋もれはじめているが。彼にはそれをどうこうする趣味はない。今回は敢え て痕跡を消す必要もない。この山を訪れる人間はいない。麓の町の住人がこの一団への恐怖から住処を捨てて逃げ出したのが一年以上前のことだ。それに遺体に 残る傷跡に人間の手によることを疑わせるものはない。この連中が発見されたとしても山の獣たちの仕業と言うことで納得されるだろう。
男は静かに手を伸ばして女の眼球に触れた。そして隠された真実を確かめた後、両眼を閉じてしばらく押さえていた。これは彼が手を下したのではない骸、言 わば通りすがりの死体のようなものだ。だから目を閉じてやったのが最大の彼のきまぐれだ。
男は歩いて行って彼のコートを拾い上げた。
その下にいた少女は目を閉じていた。死んではいない。放っておけばやがて死ぬ。
『ポッポー』
白い鳩が少女の頭の上に舞い降りた。
首を傾げて男を見上げる丸い瞳に男の口角が小さく上がった。
「心配なのか?珍しいな・・・そいつが気に入ったのか。契約は守る。心配は必要ない」
鳩に言って聞かせた男は冷たくなった少女の身体を抱き上げた。予想以上に軽かった。昨日からずっと目的の女とここの海賊上がりの男たち、それと少女の様 子を見張っていた。少女は見るからにか細い身体で男たちのために雑用をこなしていた。男は彼の同僚の女のこの少女と同じような外見の時期を振り返って大体 の年齢の検討をつけていたのだが、数時間前に少女の初潮の場面を目撃して内心驚いていた。こんな棒っ切れのような身体で。
吹雪がまた強くなった。
男は少女を抱いたまま小屋に向かって歩き出した。
腕の中で動く気配があり少女が目を開いた。不思議そうに男を見上げる顔に恐怖はない。冬の冷たさと目撃した惨状に精神が麻痺してしまったのだろうか。
二人は無言で見つめ合った。
倒れた女の身体の横を通るとき、
リリアは無言で視線を落とした。半分雪の中に埋もれはじめたネルの足はブーツを履かずに裸足だった。
少女の瞳から涙が落ちた。それは音の無い静かな哀悼だった。
パチパチと薪が爆ぜながら燃える音が耳に流れ込んできた。
目を開けた
リリアは自分がストーブの横の即席に作られた寝床の中に寝かされていることに気がついた。タオル、カーテン、隅に作ってあったネルと
リリアの寝台から剥がされた毛布。何重にもしっかりくるみ込まれていたので片手を引っ張り出すにも一苦労だった。
「起きたのか」
記憶に残っている黒い姿とストーブの前で椅子に座っている男の姿がゆっくりと一致した。よく見ると男には黒以外の色もあった。ネクタイと帽子に巻かれた 細い布の色。そして男の肌と唇の色。
寝たまま床を見ると小屋の中には朝の出来事につながるものは何も残っていなかった。湯浴みの盥もバケツもない。みんなこの男が外に出したのだろうか。
「・・・誰?」
男に問いかける少女の声は予想外に柔らかかった。もしかしたらすべてを忘れているのだろうか。男が無言のまま視線を返していると、白い鳩が彼の肩から飛 び立った。
「あ」
鳩は少女の顔の前に下りた。少女の顔に嬉しげな微笑が浮かび、白い手が鳩の背を撫ぜた。鳩は首を曲げて少女の手に頭をこすり付けた。
「よかった・・・お前はもう寒くないの?」
鳩は胸を張って羽を広げた。少女の微笑が大きくなった。
「この鳥はあなたと一緒にいたんだ・・・」
リリアは呟いた。
黒衣の姿、すばやい動き、流した血。それだけを考えるとこの男に恐怖を感じなければいけない気もしたが、なぜか
リリアはこの男が怖くなかった。目を奪われたあの雪の中での一瞬が少女の命を狙ったものではなかったからだろうか。恐らくこの男は少女 には無関心で、ネルが条件を出したからこうして少女を雪の中から救い上げたのだ。表情を変えない男の無関心さが
リリアには安心できた。
男は鳩が彼を振り向いて投げてきた視線に苦笑した。
彼にとって相棒とも言えるこの鳩は時々思いがけない影響力を持っている。そんな時、彼の唇には冷たい笑みが浮かぶのだった。
「・・・そいつはハットリだ」
「ハットリ・・・?」
リリアが復唱するとハットリは頷くように頭を上下させ、少女の手を軽くつついた。
「俺はロブ・ルッチだ。だが覚える必要はない。俺たちのことはすぐに忘れろ。明日、吹雪が止んだらお前を連れて山を下りる。一番近い街に着いたらそこがお 前の新しい住処だ。お前はそこに残り、俺たちは帰る」
リリアは答えなかった。
ずっとこの山で生きてきた。厳しいネルと一緒に男たちの言いつけをきいて暮らしてきた。だから外の世界のことは知らなかった。ほんの時折ネルが上機嫌な ときにネルがこれまでに行ったことがある街の話を聞いた。それだけだ。だから今の自分が突然街に行っても何をどうしたらいいのかさえわからないだろう。こ れまで暮らしてきたここでの生活はきっと他の人間から見たらひどく狭くて歪んでいるはずだ。
リリアは答えない代わりに弱音を言うこともしなかった。開放して命を救う・・・このルッチと言う男がネルと約束したのはそれだけだっ た。だから
リリアは男が言うとおりにするだけだ。
「飲んだらまた眠れ」
ルッチは水を差し出した。小屋の中に口に入れることができるものはそれしかなかった。
リリアはそれを受け取ると手が震えないように注意しながら飲んだ。
リリアの身体は高熱を発していた。
そのことを
リリアもルッチも知っていたが、どちらも何も言わなかった。
鳩に人の病気はうつるものだろうか。心配になった
リリアはハットリのお尻をそっと優しく押した。
「風邪がうつっちゃう・・・」
ハットリは首を横に振って翼を少女の額にあてた。
リリアははっとした。随分前にこうしてもらった記憶が蘇る。あの時ネルは穏やかな声で何か歌いながら
リリアのそばにいてくれた。そんな姿を見たのは初めてで・・・そして結局最後だったのだが・・・長く見ていたかった
リリアはくっつきそうな目蓋を懸命にこらえてずっと起きていた。ネルは何も言わず歌い続けた。
思い出した記憶とともに熱いものが溢れそうになった。その馴染みのない感情を見られたくなくて頭まで毛布に潜り込んだ。
リリアは泣くということを知らなかった。10数年の日々の中で自然に零れ落ちた涙が頬を濡らしたこともあるが驚いてすぐにそれを抑える ことを覚えた。
ルッチは光る髪以外隠れてしまった少女に黙って視線を向けていた。彼は普通の『子ども』についての知識が無かった。彼自身はそういう存在である時期はな かった。一緒にいたカリファやカクもそうだ。だから女が少女の命を条件に示したとき、正直煩わしいと思った。どうせ怯えて泣きわめくか逃げようとするに違 いないと思った。そして予想ははずれた。どうやらこの少女は感情を凍らせる術を身につけているようだった。それと同時にハットリに見せた幼いほほ笑みの方 にむしろ彼は驚いていた。これが年相応というものなのだろうか。
痩せ細った身体に訪れた大人のしるし。己に感情の乱れを許さない本能的防御。一般人には心を許さないハットリが心配そうな視線をじっと注いでいる姿には もしかしたら将来の美に繋がるかもしれない可能性も見えていた。この一見バラバラにも見える要素を秘めた少女はどう生きていくのだろう。
ルッチは自分の中に見つけた珍しい好奇心に苦笑した。考えるまでもない。保護者も金も何もない子どもの行き着く先など知れている。闇側に堕ちるか施設に 引っかかるか。どちらにしてもなまじ容姿が秀でていればいるほど死ぬまで他人に支配されて生きることになるだろう。恐らくは短い生を。
短い冬の日が暮れはじめていた。
ルッチはコートの内ポケットから取り出した携帯フラスコの口を捻って一口飲み干した。濃厚な香りとともに喉を焼かれる感覚が心地よかった。
少女がもぞもぞと顔を出したとき、頬は熱で紅潮して真っ赤になっていた。くるみ込まれた毛布の中で細い体がガクガクと震えているのがわかった。
それでも
リリアもルッチも互いに何も言わなかった。
ルッチには
リリアの複雑な表情を読み取ることができた。少女は自分が病気になったことを恥じている・・・罪の意識さえ持っているかもしれない。そ れは恐らくこれまで少女にとって許されることではなかったのだ。男たちは少女のことを役立たずと罵っただろう。そう。容易に想像できる。海賊上がりも政府 の役人も自分たちの道具だとみなした存在には普通の人間であることを許さないのは同じだ。
ルッチはやかんを見つけて湯を沸かした。沸くとポケットから取り出した携帯食を粉々に砕いてカップに入れ、その上から湯を注いだ。いかにも食欲がわかな いドロドロのものができあがったが、ふと思いついてフラスコから酒を垂らした。
リリアは熱に潤んだ目でぼんやりとルッチの動作を目で追っていた。身体の上にあるハットリの重さが関節に痛かったがひどく嬉しかった。 外の吹雪の音はすでに嵐と言えるレベルになっていた。吹きつけ、揺らし、小屋をひっくり返す隙を狙っている。
震える体は皮膚の表面の熱を身体の内部に伝えるのを止めてしまったようだ。少女は自分の肌の熱さを意識しながら身体の芯は寒くてどうしようもなかった。 顔に感じるストーブの熱はちっとも痛む身体に広がらない。こんなに震えたらハットリが転がり落ちてしまうのではないか。
リリアは歯を食いしばった。
「中から温めろ」
ルッチは小さく合図してハットリをどかすと少女の傍らに膝をついた。
無造作にカップを差し出してから初めてそれでは無理なことを意識した。少女の身体はまるで命乞いをしながら死の恐怖に押しつぶされている者のように大き く震えていた。彼を見上げる瞳には謝意があった。少女が懸命に伸ばした手が力なく落ちる寸前にルッチはそれを左手に受け止め右手のカップを床に置いた。無 言のまま少女の身体に右腕を回して抱え起こすと細い身体は床に座った彼の膝の間におさまった。
リリアは一瞬理由のない恐怖に目を閉じた。これまでに誰かが少女にこんなに近い場所にいたことはなかった。パニックを起こしかけたと き、男が少女を支えながらもその腕以外はほとんど触れないように微妙な距離を保っていることに気がつき、ほっと息を吐いた。この男も人に触れたり触れられ るのが苦手なのだろうか。
リリアはぐらつく身体をまっすぐにしようと必死になった。
「無理か」
感情を見せずに呟いたあとルッチは今度はしっかりと細い身体を腕の中に抱え込み、少女の背中を自分の胸に寄りかからせた。少女の体の熱が伝わってきた。 途端に身体を硬くした少女はそれでも今の体勢の方が楽だったのだろう。またひとつ息を吐くとルッチに体重を預けた。
「飲め」
男の手が差し出したカップからは酒の匂いがした。それはかなり強い香りだった。受け取った
リリアの手が震えてカップを落としそうになると、男はそれを受け止めてため息をついた。そして
リリアの唇にカップの縁をあてた。
ルッチは少女の口もとを見下ろしていた。震える唇がゆっくりと小さく開く。カップを少し傾けてやるとわずかな量を口に含んでから飲み込んだ。それから少 女の身体は大きく揺れ、慌てて口に手をあてたところをみるとどうやら口には合わなかったらしい。それでも落ち着いた頃にまたカップを寄せると少女は逆らわ ずにまた一口飲んだ。雛鳥だったハットリに湯に浸した粒餌を食べさせた時に似ている。ルッチは唇をゆがめてその記憶を追い払った。
口の中のものを無理やりに飲み下しながら、
リリアはカップをもつ男の手を見ていた。指の長いその大きな手は
リリアが知っている男たちの手よりごつくは見えない。白く滑らかに見えたが、朝、その手は血に染まっていたのだ。命を奪い、今は命を与 えてくれようとしている手。さっきハットリに触れたときはとてもゆっくりと動くのが見えた。
ルッチは少女の身体の震えが小さくなったのを感じていた。こうしていると寒さが和らぐのだろうか。少女が時々咽ながらカップの半分ほど中身を減らしたの を確認するとルッチはカップを床に置いた。
「アルコールが回っているうちに眠ることだ」
言いながらルッチは少女を抱いたまま静かに身体を倒した。
床に敷いたボロボロの毛布の上で少女をすっぽりと包み込み、自分と少女の身体にコートを掛けた。少女はまた身体を硬くしていた。早まる心臓の鼓動を直に 感じた。
「何もしない。お前に興味はない」
囁いたルッチは少女の身体の熱で彼の身体も温まりはじめたことに気がついた。損はないということだ。彼を求める女を抱くよりも暖を取るには都合がいい。 無駄に体力を減らす必要もない。
「あの・・・ルッチ・・・」
少女の声が紡ぎだした音が彼の名前だということに・・・ルッチは一瞬気がつかなかった。躊躇いがちにそっと静かに。少女はまるで大切そうにそれを囁いた から。
その時、ハットリが少女の上に舞い下りた。
「お前は眠って熱を下げることだけ考えろ。天気が回復しだいここを離れたいからな」
少女は頷いた。素直に目を閉じたことがわかった。
名前は
リリアといったか。
ルッチは少女の銀色の髪に落ちて混ざっている自分の髪を眺めた。
少女の顔を覗き込んだハットリが安心したように自分も丸くなって羽の中に嘴を埋めた。
やがて吹雪の音よりも少女の寝息が規則的により近く聞こえはじめた。
煩かったらすぐ止められる。
ルッチは幼いぬくもりに触れながら目を閉じた。