泳ぐというひとつの能力を失った時はさほどの喪失感はなかった・・・という微かな記憶がある。引き換えに手に入れることが出来るはずの未知の能力に対する 好奇心の方が遥かに強かった。そして得た能力は己の奥底にひそかに横たわっていた紅の欲望を外に解放するものだったのだが、彼はそれを微量の恐れとともに 己に内包した。その恐れが能力そのものについてのものだったのか、それとも剥き出しにされた己の内側についてだったのか。今はもう覚えていない。
耳元を通り過ぎる水音と肌にまつわりつくような冷えた感触が『海』をひどく意識させた。
落ちずに宙を蹴って陸に上がることは出来た。けれどこの身体能力は人前に晒すものではない・・・まだ今は。まして晴れた日の海そっくりの色をした瞳を丸 く見開いて大口をぽっかり開けたマヌケ面の前では。
「ル・・・・!」
短い名前の半分は水音に消された。ただ、口の形が残りを伝えていた。
考えてみれば海に落ちることは死に等しい・・・のだったと。ルッチは思った。悪魔の実を口にした者は例外なく海に嫌われる。捕らわれてしまえば溺れるし かない。なのに彼はそれを選んでしまった。そして不思議と恐れはない。水の中を沈みながら水面から差し込む光を見ていた。
青い海。通り道をくっきりと見ることができる光。眩しく揺れながら遠くなる水面。
手を伸ばしても届くことはない。わかっているから胸の前で腕を組んだ。
ザブリ。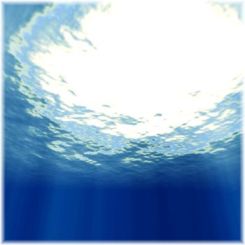
光を背負った暗い影が目に映る情景に割り込んだ。
まだ間に距離があるというのに目一杯腕を伸ばしてくる気が早い男。足で水を蹴ってぐんぐん近づいてくる姿はなぜか陽光そのものに見えた。
あの光になら届くことはできるのか。もしかしたら。
それでもルッチは腕を組んだままでいた。
死にたいとは思わない。けれど生きたいとも思わない。いつも傍観者でいたかった。すべてを超越してどこに縁を結び付けられることなく。紅の欲望に意識を 支配されている時も常に心の片隅で己の姿を自嘲しているように。
バカヤロウ。
そんな言葉を形作っている唇を見ながら目を閉じた。海を恐れることなく今ここに在ることに小さな満足を感じていた。
「ルッチ!おい、ルッチ!バカヤロウ、目を開けろよ、ルッチ!」
全身の力を振り絞って脱力した身体を岸に引きずり上げた。肩で大きく息をしながらパウリーは懸命にルッチの名を呼んだ。
「冗談じゃねぇぞ・・・おい、ルッチ!」
ずぶ濡れの身体に張り付いた衣類。パウリーの目から見るとなぜか触れたいのに触れてはいけない彫刻のように見えることがある顔。目を閉じたその顔を取り 囲むように張り付いている乱れた黒い髪。
バササ・・・と頭の上で羽ばたいているのは主を失いかけている一羽の鳩で。その鳩が一言もパウリーを揶揄する言葉を吐こうとしないのがまったく不自然 で。
ハッとしたパウリーはしばし躊躇った後で片手をルッチの肩に置き、もう一方の手でグラグラと揺れる頭を抱えた。
・・・このままだといかにも不慣れな口づけを受けてしまうことになる・・・人工呼吸と言う名の。
奥のほうから意識が戻りはじめたルッチは目を閉じたまま己が置かれた状況を正確に把握した。唇を与えることも与えられることも、その相手が男であっても 女であってもさほど何も感じることがないルッチだった。それなのにそれがパウリーであることをなぜこんなにも意識してしまうのか。不器用な手つきで彼の額 をゆっくりと撫ぜているパウリー。もしかしたら涙ぐんでさえいるのではないか・・・ルッチは心の中で自分の馬鹿げた想像に苦い笑いをした。
「戻って来い・・・ルッチ」
なぜそんなに何度も名前を呼ぶ。
普段から想像も出来ないその声はどこから来る。
搾り出すようなその囁きは、何だ。
思い巡らせているうちに気配が近づき唇に温かなものが触れた・・・と思う間もなくルッチの耳の中に鈍い音が響いた。
『・・・歯をぶつけるな、バカヤロウ』
ギリギリのタイミングで舞い下りた鳩が呟いた。
顔の下で突然開いたルッチの黒瞳と唇から漏れた低い声に驚いたパウリーが勢い良く頭を上げた。ゆっくりと持ち上げた手で唇を拭いながらルッチはパウリー の顔を見上げた。やっぱりマヌケ面だ、と真っ赤に染まったその顔を再確認しながら。
「な、何だよ、お前!んなに突然目を開けるんじゃねぇ!」
『このままずっと目を開けない方がよかったか』
首筋まで赤くなっているパウリーの状態をさらに確認しながら起き上がったルッチの肩にハットリがとまった。
「バ・・・。んなわけねぇじゃないか!バカルッチ!」
バカヤロウにバカルッチ。
そう言えばいつ頃からかパウリーの口癖が増えたようだった。その口調にひどく聞き覚えがある気がするのは気のせいか。
「お前・・・いつから気がついてたんだ?」
『・・・歯がぶつかった時からだ』
「う・・・それは忘れろ」
茹でたてのカニみたいな顔色で肩を落としたパウリーは・・・いや、溺れかけたことで感覚が麻痺してしまったようだ。ルッチは唇から意識を飛ばした。
パウリーはそのまま地面に座り込んだまま胡坐をかいた。
「にしてもよ、お前、何で突然海に落ちるんだよ。俺はただお前の誕生日がいつなのかきいただけじゃねぇか。おまけに何で泳げねぇんだよ。泳げねぇのに船大 工やってるなんて信じられないやつだな」
どちらの質問にも答えかねる。
ルッチは立ち上がると頭を一振りした。濡れた髪から飛んだ水滴が光をはじいた。
『俺の誕生日などどうでもいいだろう』
背を向けてしまったルッチの後姿を見上げたパウリーの顔に一瞬見捨てられた子どものような表情が浮かんだ。それでも葉巻を咥えたときにはすでにいつもの 無邪気としかいいようのない笑いが戻っていた。
「うぇ、何だよ、葉巻、濡れちまった。いいじゃねぇか、誕生日くらい。この間の俺のときにさ、結構楽しかったからよ。だからお前の時にも一緒に飲みてぇと 思ったんだよ・・・二人で」
そこでまた顔を赤くするな。ルッチはため息をついた。このままだといつまでたっても後ろを振り向けそうにない。
『俺には自分の誕生日にさわぐ気はさらさらない』
「だろ?俺と同じだ、やっぱり。お前、そういうヤツだよな〜」
パウリーは・・・自分の誕生日にルッチの部屋に半ば強引に入り込んで勝手に飲んで食べて大騒ぎして眠ってしまったのではなかったか。ルッチは軽く頭を 振った。これではいつも通りパウリーのペースだ。このままでは面白くない上にいろいろ突っ込まれて面倒だ。だから。
「・・・何だよ」
振り向いたルッチの眼光の鋭さに一瞬気圧されたパウリーは大きく瞬きをした。その一瞬の隙を逃さずに音もなく近づいたルッチは右手をパウリーの頭の後ろ に回し、屈み込んで深く唇を合わせた。その途端に見事に硬直したパウリーの身体を外した右手でトンと突き、ルッチはふわりと離れた。
「ル・・・おい!」
焦ったパウリーの声に束の間、足を止める。
『これが一般的なキスというものだ。せいぜい数を重ねることだ』
再び歩きはじめたルッチは予想通りパウリーが追ってこないことに満足した。驚いて動揺して立ち上がることすらできなくなっている単細胞。大きくなっただ けのガキ大将。
ルッチには振り向く気はなかった。
自分の行動の意味を考える気もなかった。
今日が彼の誕生日その日であることをパウリーに教えるつもりもなかった。
海の中で見た金色の光。
それを思い出しさえすればいつでも海の懐の中で死ねる気がした。泳ぐと言う能力は本当に大したことがない。いつか彼は海の中で微笑しながら死んでいくこ とを願いさえするかもしれない。
誕生日に一人のどうしようもない男に気まぐれで唇を与えたことを、もしかしたら自分はずっと覚えているのかもしれない。
空を振り仰いだルッチの顔に穏やかな笑みが通り過ぎた。